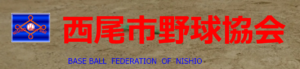登校中の小学生を見て我思ふ
出勤時に、班で登校するたくさんの小学生の横を通るのですが、昔、緑のおばさんっていう女性が、通りの多い横断歩道に立っててくれたな、いつも同じ人だった気がする、おばさんって呼称がまかり通る昭和ってすごかったな、などと昔を思い出しながら見ています。隊列が乱れているグループもありますが、一般的に先頭を6年生と思しき子が務め、中間にちっちゃい子がいて、最後尾を5、6年生が務めるという構図になっています。
隣を出勤の車がブンブン通り過ぎるなか、1、2年生が車道に飛び出さないか、縁石をかかしみたいに手を広げて歩いて転んだりしないか、遅れる子はいないか、などを考慮しつつ、隊列を崩さず登校する姿を見ていると、常に思うのは、「僕は一番後ろの係が好きだなー」です。
組織が前進するためには、先頭に立ち進路を決定するリーダーが必要です。しかし、後ろを気にして振り返ってばかりいたり、スピード調整などに気を使っていたら疲れるし、進むべき方向を謝ってしまうかもしれません。最前列において班を引っ張るリーダーは、常に決断を繰り返しながら前進するのです。
そこで、後方から全体を見て、調整または異常事態をリーダーへ知らせるべく、今どうするべきかを判断する最後尾の人の役割が重要になってきます。
そこには、判断と決断という似て非なるものが存在します。 
判断とは
与えられた情報の比較分析から、最も合理的かつ効果的な選択肢を選ぶこと。
判断する際の根拠は「過去のデータ」や「経験」。
安全圏の中で最適な選択肢を探すことになります。
会社で言うと中間管理職のポジションです。
決断とは
自らの選択肢を正解に導くこと。
決断に明確な情報などはなく強いて根拠と言えば自分自身、そんな中で自分の意思で方向性を定めること。
そして選んだ選択肢を、何が何でも正解に導くこと。
会社で言うと社長。
「判断」が過去を分析して選択肢を選ぶことであるのに対し、「決断」は未来を見据えて行動を起こすことです。
リーダーとはそういうポジションです。
決断を求められる状況
このプロジェクトを自分の思いだけで、突っ走るように始めた結果、自分の意志で、「決断する人」になったわけでして、苦手ながらも目標実現のため決断を繰り返している毎日であります。全国の社長と呼ばれる皆さんに敬意を表し、微力ながらがんばります。
正式名称「学童擁護員」
緑のおばさんの正式名称は「学童擁護員」さんだそうです。まだ、おられるのかな?